鉛筆といえば、学生時代から大人になるまで幅広く使われる文具の代表格です。実は、その芯には驚くほどたくさんの種類があり、それぞれの硬さや濃さは微妙に異なります。普段はあまり気にせず「2B」や「HB」を選んでいる方も多いかもしれませんが、実は製図用や絵画用など、目的に応じて最適な芯が存在するのです。
本記事では、鉛筆の芯の成り立ちや、「H・F・B」などの表記が示す意味、色鉛筆との違いなどを幅広く解説していきます。読み進めることで、きっと今まで何気なく使っていた鉛筆の世界が、ぐっと身近に、そして奥深いものになるでしょう。
1. はじめに:鉛筆にこんなに種類があるって知ってた?
子どものころから慣れ親しんできた鉛筆ですが、あなたは何種類の硬度があるかご存知でしょうか。文房具店に行くと、2BやHBなど、数種類しか見かけないという人もいるかもしれません。しかし実際には、JIS(日本産業規格)で定められた17種類もの硬度があるのです。
なぜこんなにも多くのバリエーションが必要なのでしょうか? それは、使用目的や表現したい濃さによって、より最適な芯の硬さ・濃淡が求められるからです。日常のメモ書きやお絵描き、製図やデッサンなど、使う人のニーズに応えるために、各メーカーは多彩なラインナップを展開しています。
この記事では、鉛筆の芯の素材や製造工程、そして硬度が変わる仕組みを詳しく解説していきます。さらに、色鉛筆の芯がなぜ消しゴムで消えないのか、といった疑問にも触れていきます。「どの鉛筆を使えばいいか迷う」「なんとなくしか知らなかった」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

2. 鉛筆の芯は何でできている?
黒鉛と粘土が生み出す濃淡と硬さ
鉛筆の芯をじっくり見てみると、黒くてサラサラしています。「鉛」という名前がついているので金属のイメージがあるかもしれませんが、実は黒鉛(グラファイト)と粘土が主成分です。ここに鉛が含まれているわけではありません。
- 黒鉛(グラファイト)
炭素の結晶体であり、ダイヤモンドと同じ炭素仲間です。ただし結晶の構造が異なるため、黒鉛は柔らかく、ダイヤモンドは硬いという違いがあります。黒鉛は紙にこすりつけると細かく剥離し、濃い色を残す性質を持っています。 - 粘土
一度焼くと固まる性質を持ち、陶磁器や瓦の材料としても使われる身近な素材です。粘土の含有量が増えるほど、芯は硬くなり色は薄くなる特徴があります。
この2つの比率や質の違いで、鉛筆の筆記感や濃淡の差が生まれます。
焼き上げの工程が鍵を握る
黒鉛と粘土を混ぜ合わせた後は、長い棒状に成形し、さらに1000℃以上の高温で焼き上げる工程を経ます。こうすることで芯は固まり、芯としての強度と書き味が生まれるのです。焼き上げる温度や時間もメーカーごとに工夫があり、微妙な差が芯の品質を左右します。
3. 濃さや硬さはどうやって変えている?
粘土の割合と黒鉛の割合
鉛筆を選ぶとき、「H」や「B」などの記号はなんとなく知っていても、それが黒鉛と粘土の配合比率を指し示していることはあまり知られていないかもしれません。ざっくり言えば、以下のようなイメージです。
- 黒鉛が多い → 柔らかい → 濃い文字になる
- 粘土が多い → 硬い → 薄い文字になる
たとえば「HB」の場合、黒鉛と粘土の配合比が中間程度になります。メーカーによって若干の差はありますが、黒鉛がやや多めの「B」系統ほど芯が柔らかくなり、筆圧が軽くても濃い文字が書ける一方、芯が減りやすいという特徴もあります。
芯が紙に色を残す仕組み
鉛筆で文字を書くという行為は、芯の表面から微細な黒鉛の粒子が少しずつ削れ、紙の繊維のすき間に入り込んで定着することによって成り立っています。硬い芯の場合、削れにくい分だけ紙に付着する黒鉛の量が少なく、結果的に淡い色になります。柔らかい芯は逆に黒鉛がよく削れるので、濃い線が残るというわけです。
4. 鉛筆の硬度表記:「H」「B」「F」って何?
主な17段階とその特徴
日本産業規格(JIS)では、鉛筆の硬度を大きく17段階に分けています。一般に流通しているもので代表的なのは、9H、8H、7H、6H、5H、4H、3H、2H、H、F、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B となります。
- H系(硬い)
「9H」がもっとも硬く、数字が小さくなるにつれて徐々に柔らかくなります。硬い芯は線が細く、紙にしっかり溝を作りやすい特性があるため、製図や下書きなどで重宝されます。ただし濃さが足りないと感じる人もいるでしょう。 - B系(濃い)
「6B」がもっとも柔らかく濃いため、絵を描く際の陰影や濃淡表現に好まれます。筆圧が弱くてもはっきりとした黒が出せる反面、芯が消耗しやすいためこまめな削りが必要になります。 - F(Firm)
「F」はHとHBの中間あたりと言われ、独特の書き味があります。硬すぎず柔らかすぎずといったイメージで、海外ではFの鉛筆を好んで使う人も少なくありません。 - HB(Hard & Black)
「HB」は名前が示すとおり、硬さと黒さのバランスがとれています。文房具売り場でもっとも一般的に目にする硬度であり、学校やオフィスでも幅広く使用されます。
目的別おすすめ硬度の活用例
用途別に硬度を選ぶと、作業効率や表現力がぐっと高まります。以下は一例です。
- 学習・事務作業:HBやB
- 長時間の筆記でも疲れにくく、文字が見やすい
- ノートやコピー用紙との相性も良好
- 製図・建築設計:H〜3H
- 定規を使った線がにじみにくく、精密な線が引きやすい
- 線が細いので、設計図の細かい表現にも適している
- イラスト・デッサン:2B〜6B
- 濃淡をつけやすく、やわらかな表現が可能
- 塗りつぶしや影の表現もしやすいため、芸術分野に向いている
5. 消しゴムで字が消える仕組み

黒鉛の付着力より消しゴムの摩擦が強い
学校で使うシーンも多い鉛筆ですが、書き損じたときにサッと消しゴムで消せるのは大変便利ですよね。これは、紙の繊維に入り込んだ黒鉛の粉よりも、消しゴムの持つ摩擦力のほうが強いためです。消しゴムをこすると黒鉛の粒子が紙から剥がされ、ゴムの屑にくるまって一緒に取り除かれます。
消しゴムの成分と働き
現代の消しゴムは、主成分としてポリ塩化ビニル(PVC)などのプラスチック素材やイレースポリマーを利用するものが多いです。これらが摩擦によって紙の表面をこすり、黒鉛を効率的に取り除きます。消しゴムの品質によっては、紙を痛めやすいものから、滑らかな使い心地で紙へのダメージが少ない高級タイプまでさまざまです。
6. 色鉛筆の芯はどう違う?
色鉛筆が生み出す色の秘密
黒鉛ではなく、多彩な色を表現する色鉛筆。主な成分は次のようになっています。
- 顔料(ピグメント)
発色の元となる粉状の色素。赤や青など、複数の顔料を混ぜ合わせて理想の色を作る。 - ワックス(ロウ)
クレヨンのように、滑らかな筆記感を生むために配合される。 - タルク
柔らかい鉱物で、指先に触れると滑らかな質感がある。芯に適度な硬さを与える役目も担う。 - 接着剤
顔料やタルク、ワックスを固め、芯の形状を維持するために使われる。
黒鉛と粘土が主成分の鉛筆とは異なり、色鉛筆は色の素となる顔料が主体です。ワックスやタルクが配合されることで、紙の表面を滑らせるように色が乗っていきます。
焼き固めない理由と折れやすさ
鉛筆の芯は高温で焼き固めますが、色鉛筆の場合は焼き固めの工程がありません。これは、顔料が高温で変質して色が変わってしまうのを防ぐためです。結果として、色鉛筆の芯は鉛筆と比べると折れやすい傾向にあります。
ただし、芯を保護するために木軸にも工夫がされており、全体に均一な力がかかるよう設計しているメーカーもあります。もし芯が折れやすい場合は、筆圧を抑えたり、削る際に鉛筆削りの負荷を調整したりするなどの工夫が必要です。
色鉛筆の硬さの分類
色鉛筆には鉛筆のような17段階の硬度表記はありませんが、大きく下記のような分類があります。
- 硬質:硬めで先が折れにくく、細かい線が描ける。製図や細部の彩色に向く。
- 中硬質:一般的な事務用や図画用として最もポピュラー。学校で使用する色鉛筆もこのタイプが多い。
- 軟質:柔らかく濃い色合いが出せる。木や陶器など紙以外の素材に描く場合にも使いやすい。
配合されるワックスや接着剤の比率によって、これらの硬さや書き味が変わります。たとえば、イラストレーターやアーティスト向けに開発された高級色鉛筆は、発色や混色のしやすさを重視した配合となっています。

7. 実際に使い分けるときのポイント
ここまで鉛筆と色鉛筆の芯の違いや硬度について解説してきましたが、実際のシーンではどのように使い分ければいいのでしょうか。ここでは、具体的な用途や目的別に選ぶ際のポイントを紹介します。
学習用・事務用の選び方
- 初心者や子どもには2BやBが人気
書くときにある程度柔らかさがあるほうが、力の弱い子どもでもはっきりとした文字を書きやすいという利点があります。 - ノートやレポート用紙にはHB〜Bが無難
文章を書く量が多い場合は、適度な濃さと芯の持ちのバランスが大切。HBやBあたりなら削る頻度も少なく、視認性も悪くありません。
製図やイラストに適した硬度
- 製図ならH系の硬めの芯
シャープな線が求められる製図では、硬めの芯を選ぶと定規で線を引いたときに芯がつぶれにくく、精密さを保てます。 - イラストやデッサンならB系の柔らかい芯
濃淡のコントロールがしやすく、筆圧次第で細い線から広い面までさまざまな表現が可能です。
色鉛筆での表現をさらに広げるには
- 軟質の色鉛筆を使うと、色の重ね塗りやグラデーションがスムーズになります。
- 水彩色鉛筆を取り入れるのも一案。紙に描いたあとに水筆や筆を使ってぼかすと、水彩画のような表現ができるため、アート表現の幅が広がります。
- 中硬質タイプは学校の図工や一般的なイラストにちょうど良い塩梅です。初心者や気軽にカラフルな絵を描きたい方におすすめです。
8. ちょっと豆知識:鉛筆の歴史と進化
「鉛」が入っていないのに「鉛筆」?
「鉛筆」という名前を初めて聞いたとき、「鉛という金属が入っているの?」と思ったことはありませんか。実は昔、黒鉛が発見された当初、成分がよくわからず「鉛の一種だろう」と考えられていたため、鉛筆と呼ばれるようになったと言われています。しかし現在は、黒鉛が主成分であることがはっきり解明されています。
現代の鉛筆が形作られるまで
ヨーロッパの一部地域では16世紀ごろ、イギリスのボロー・デール地方で高純度の黒鉛が発見され、棒状に削ったものを木にはめ込んで使い始めたのが鉛筆の原型とも言われています。産業革命に伴う機械化が進んだ後、粘土と黒鉛を混ぜて焼く工程が導入され、現在の鉛筆の姿に近づいてきました。
日本でも明治維新の後、欧米の技術が取り入れられたことで鉛筆が普及。紙の普及や義務教育の拡大と相まって、日本人の生活に深く根付いていきました。
機械化と伝統の融合
一見シンプルな木の棒に見えますが、品質の高い鉛筆づくりには多くの工程と職人技が詰まっています。近年では機械化も進み、生産効率は格段に上がっていますが、最終的な検品や微妙な調整には熟練者の手が欠かせません。芯の均一性や木軸との接着具合など、細部まで配慮が行き届いています。
9. よくある質問Q&A
ここでは、鉛筆や色鉛筆に関してよく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。日常でのちょっとした疑問の解消に役立ててください。
Q1:使わないときは芯が劣化する?
A:基本的には、長期間放置しても芯自体の劣化はほとんどありません。
ただし、高温多湿や直射日光が当たる場所に長期間置くと、木軸が反って割れやすくなったり、色鉛筆のワックス成分が変質して筆記感が変わる可能性はあります。保管時は、なるべく乾燥した涼しい場所に置いておくと安心です。
Q2:シャープペンシルの芯も同じ仕組み?
A:基本構造はよく似ています。
シャープペンシルの芯も黒鉛と粘土を混ぜて作る点は鉛筆と同じです。ただし、直径が非常に細い分、折れにくさや筆記感などでより慎重な調整が必要とされています。メーカーによっては、芯の滑らかさを向上させるために潤滑剤を配合していることもあります。

Q3:色鉛筆の「重ね塗り」がうまくできない
A:筆圧やワックス成分の相性に注意すると改善しやすいです。
色鉛筆を強い力で塗り込むと、ワックス成分が紙の表面をコーティングしてしまい、後から色を重ねても弾いてしまうことがあります。重ね塗りをしたい場合は、最初は軽めの筆圧で塗り、徐々に色を重ねるのがポイント。また、紙質によっても仕上がりが変わるため、イラスト向けの紙や画用紙などを試してみると良いでしょう。
10. まとめ
鉛筆の世界は、一見シンプルに見えて実に奥深いものがあります。黒鉛と粘土の絶妙な配合比や高温での焼き上げ工程によって、硬度や濃淡が変化する仕組みは、まさに熟練の技術と長い歴史の結晶です。また、色鉛筆はそのカラフルな表現力を支えるために、全く異なる材料と製造工程を持ち、独自の魅力を放っています。
- 鉛筆の主成分は黒鉛と粘土
→ 黒鉛が多いほど柔らかく濃く、粘土が多いほど硬く薄くなる。 - 色鉛筆の主成分は顔料とワックス
→ 高温で焼き固めないため、濃淡よりも色再現性が重視される。 - 17種類の硬度(9H〜6B)を知れば、目的に合わせた最適な一本が見つかる。
- 消しゴムで消せるのは、黒鉛の付着を摩擦で剥がせるから。
- 色鉛筆は消しゴムで消しにくいが、逆に重ね塗りやぼかしなど多彩な表現が可能。
普段何気なく使っている鉛筆も、少し知識を増やすだけで、ぐっと使いこなしの幅が広がります。「硬い芯で繊細な線を描きたい」「柔らかい芯で滑らかな文字を残したい」「色鉛筆で独創的なイラストに挑戦したい」など、やりたいことや好きな書き味に合わせて選ぶのもまた一興です。
ぜひ、文房具売り場でいつもと違う硬度の鉛筆や気になる色鉛筆を手に取って、書き味や表現の違いを試してみてください。そこには思いがけない発見と、文房具の奥深さが待っているかもしれません。
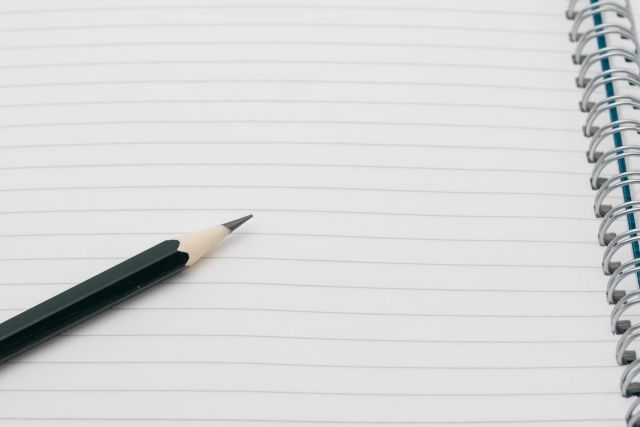


コメント